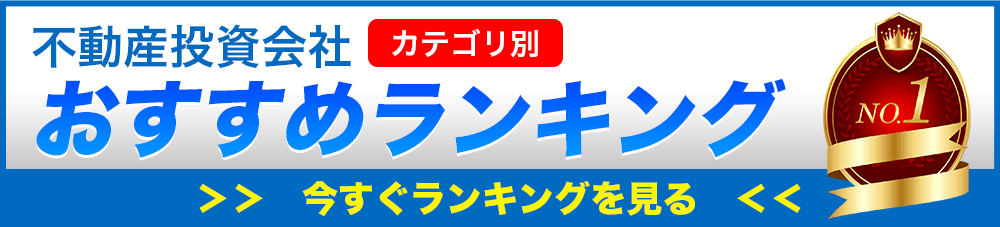不動産投資を行っているサラリーマンの場合、会社で年末調整を行っているため、確定申告が必要なのか不要なのか、迷っている人もいるかもしれません。
今回は、不動産所得があるサラリーマンの人で、確定申告が必要なケース、確定申告のしかたについて解説していきます。
また、年末調整との違いについても知っておきましょう。
不動産投資では毎年確定申告が必要 !

サラリーマン投資家で、1月1日~12月31日の間に給与以外の合算所得が20万円以上あった人は、翌年2月16日~3月15日に確定申告が必要となります。
給与以外の所得では、家賃収入による不動産所得以外にも、ライターなど副業による事業所得、フリーマーケットやオークションでの売り上げによる雑所得などが当てはまります。
これらの副業的な所得については、会社の給与とは関係ありませんので、翌年の確定申告の時期に、投資家(オーナー)が自分で税務署へ申告する必要があるのです。
不動産所得が20万円以下ならしなくてもOK
年末近くに投資物件の運用を始めた場合など、その年の不動産所得が20万円に届かなかった、あるいは赤字のケースもあるでしょう。
この場合は確定申告をする必要はありません。
しかし、本業の給与所得との損益通算により所得税を抑えることができれば、還付を受けることができる可能性もありますので、できるだけ確定申告をすることをおすすめします。
不動産所得とは?
「不動産所得」について、改めて具体的に説明しましょう。
マンションなど投資用物件を所有し、毎月得る家賃収入から必要経費を差し引いたものが「不動産所得の金額」となります。
総収入額(家賃収入、更新料、敷金、共益費等)- 必要経費(固定資産税、修繕費、減価償却費等)= 不動産所得の金額
正しく確定申告をしないとどうなる?
不動産所得が20万円以上あるのに、面倒だからといって確定申告をしなかった場合は「脱税(租税ほ脱)」になり、最悪のケースでは「前科」がついてしまいます。
国税査察官が徹底した調査を行っていますので、無申告は必ず明るみに出ます。
期限後申告では加算税、延滞税などが課されますが、5年以内(故意の申告漏れは7年)以内に確定申告と追納することで、刑罰とはならないことが多いです。
しかし、たとえ故意ではない場合でも、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金を科されるされる場合もあります。
また、悪質な場合は、刑罰として5年以下の懲役、500万円以下の罰金のどちらかが科される可能性があります。
申告漏れに気づいた場合は、できるだけ早急に確定申告を行いましょう。
年末調整との違い
年末調整は、確定申告と同じように所得を申告するもので、生命保険料控除、地震保険料控除、住宅ローン控除(初回を除く)などを含め、会社が本人に代わり行ってくれます。
ただし、その対象は「給与所得」のみとなります。
この点が、確定申告と年末調整の違いです。
そのため、給与所得以外に収入がある場合は、別途確定申告が必要となるのです。
不動産投資家が確定申告する際に必要なもの
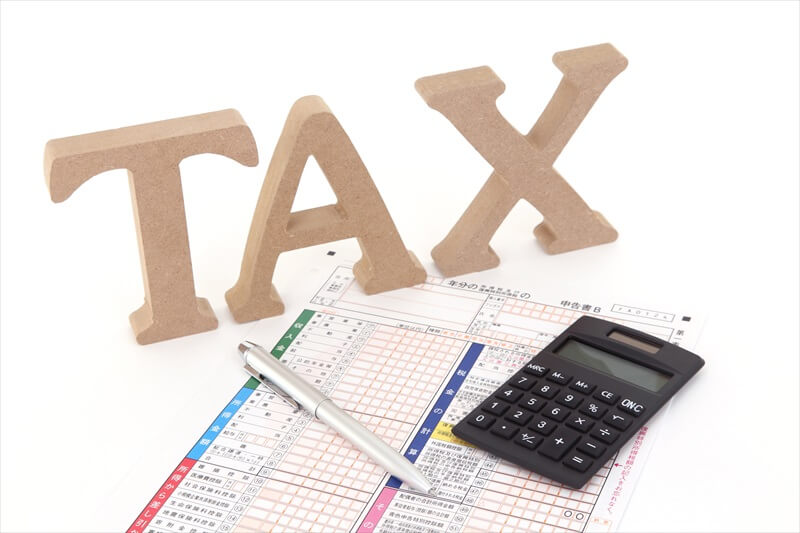
不動産所得があるサラリーマンが確定申告をする際に必要なものをご紹介します。
申告書に添付する必要がありますので、事前に準備しておきましょう。
源泉徴収票
本業である会社で年末調整を行い、翌年1月にもらえるのが源泉徴収票です。
その年の全収入を申告しますので、源泉徴収票の提出も必要となります。
また、不動産所得と給与所得を損益通算し、所得税の還付を受けられるケースもあります。
経費関連書類
税金の納付書
国や地方自治体から送付される不動産取得税、固定資産税などの納税通知書です。
住民税や所得税は経費として認められません。
ローン返済計画表
建物についてのローン金利は経費となります。
ローン返済表は融資元の金融機関から送付されます。
管理費・修繕積立金等の領収証
清掃代や修繕積立金など、物件の管理に関係する出費は経費となります。
管理会社に物件管理を委託している場合は、管理会社から発行されます。
譲渡対価証明書
投資用にマンションを購入した際に、不動産会社から発行される書類です。
土地と建物の按分割合が記載されており、建物の減価償却計算で使用します。
不動産関連書類
不動産売買契約書
投資用物件を購入する際に不動産会社から渡され、終結時に使用した売買契約書です。
賃貸契約書
入居者と賃貸借契約を交わした際に使用した書類です。
家賃送金明細書
管理会社に管理を委託している場合は、管理会社から毎月送付されます。
売渡清算書
投資用物件を購入した時の必要経費を明細にしたものです。
売買契約後~決済前までの間に不動産会社から受け取っているはずです。
控除関連書類
損害保険料の領収書
投資用物件にかけている火災保険や、セットされた地震保険の保険料は経費になります。
何年か分をまとめて支払っている場合は、その年の分のみが経費として認められます。
不動産投資家の確定申告フロー

自営業者や個人事業主にはおなじみの確定申告ですが、給与所得者であるサラリーマンにはあまりなじみがないのではないでしょうか。
そこで、確定申告の流れを簡潔に解説します。
① 白色申告 or 青色申告の方式を決める
確定申告には青色申告がオススメですが、青色申告以外にも申告方法があります。
青色申告以外の申告方法を白色申告といいます。
白色申告は簡易的でシンプルな申告方法ですが、控除などの特典が青色申告に比べて少ないのがデメリットです。
青色申告と違って帳簿処理も簡易でよく、開始申請も不要な点はメリットといえます。
② 確定申告に必要な書類を揃える
確定申告を行うには申告書を作成しなければなりません。
申告書を作成するための第一歩として、収入や支出に関する書類の収集を行います。
白色申告の場合
必要な書類は大きく分けて5点です。
- 確定申告書B
- 収支内訳書(不動産所得用)
- 源泉徴収票
- 身分証(免許証orパスポート)
- マイナンバーカード(通知カードor番号記載の住民票でも可)
確定申告書Bと収支内訳書は税務署でもらえるほか、ネットからダウンロードできます。
控除に必要な証明書類や領収書は、給与所得者は年末調整で控除手続きを終えていることが大半ですので不要です。
年末調整の時に出し忘れた場合は一緒に添付し、領収書や帳簿は添付しません。
しかし、7年間の保管義務がありますので、しっかり保管します。
青色申告の場合
青色申告の場合も収入や支出に関する領収書や証明書を収集します。
必要な書類は下記のとおりです。
※65万円控除と10万円控除で提出書類が増減します。
- 確定申告書B
- 収支内訳書(不動産所得用)
- 源泉徴収票
- 身分証(免許証orパスポート)
- マイナンバーカード(通知カードor番号記載の住民票でも可)
年末調整で控除の手続きは済んでいますので、控除に関する証明書類は不要です。
ただ、年末調整に出し忘れた場合は添付して控除を請求できます。
確定申告書Bと青色申告決算書は税務署で入手できるほか、ダウンロードでも入手可能です。
青色申告の場合は、青色申告決算書と損益決算書、貸借対照表を作成します。
近年では、不動産投資の必要経費に関する領収書の添付は不要になりましたが、7年間の保管義務があるため、帳簿と一緒にきちんと保管しましょう。
③ 確定申告書、青色申告決算書、不動産収支内訳書に記入する
白色申告の場合は、不動産収支内訳書に帳簿内容を記載して、完成させます。
不動産収支内訳書をもとに確定申告書Bを作成します。
確定申告B収入欄の給与の欄に源泉徴収票の支払金額、不動産収入欄に不動産収支内訳書の不動産収入を転記しましょう。
同様に所得の給与所得と不動産所得をそれぞれ転記していきます。
控除欄の社会保険控除や生命保険控除があれば源泉徴収票から転記します。
ほかに年末調整に提出し忘れた控除があれば記載しましょう。
最後に確定申告書Bの記載に従って申告書を完成させます。
通常は控除後所得に記載し、税額を計算します。
源泉徴収欄に記載した金額を差し引き、納税額を記載して完成です。
源泉徴収票がある場合は確定申告書Bの第2表へも記入しましょう。
青色申告の場合でも手順は変わらず、記載は白色申告と同様に記載します。
ただし不動産収支内訳書はなく、代わりに、収入や経費を記載する「損益計算書」「損益計算書の内訳」「貸借対照表」を作成します。
それぞれ税務署で入手できるほか、ダウンロードもできます。
④ 税務署に書類を提出する
作成した確定申告書は添付書類と一緒に税務署の窓口へ提出します。
書面で申請する場合はコピーを取っておくと何かと便利です。
なお、窓口へ持参した場合は確定申告書に受領印を押した控えがもらえます。
書面の提出は持参だけでなく郵送でも構いません。郵送の場合は管轄税務署へ郵送します。
書面をPCやスマホで作成して、ネットで提出する電子申請(e-Tax)もあります。
e-Taxは最初ひと手間かかりますが、税務署へ出向かず、会計ソフトで作成できるメリットあり、今後主流になっていくと思われます。
詳しくは、税務署の案内ページをご覧ください。
不動産投資でかかる税金はいくら?
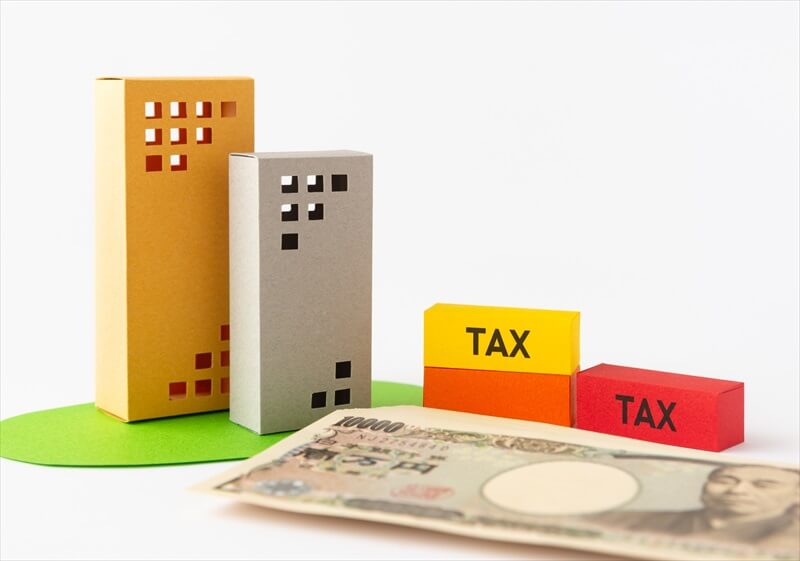
不動産投資による所得にかかる税金はどれくらいでしょうか。
簡単に計算してみましょう。
課税所得金額は所得金額から経費や控除額を差し引いた金額のことです。
たとえば、給与所得が500万円、不動収入が500万円、経費が300万円、控除が全部で50万円だった場合は、「500万+500万-300万-50万」で650万円が課税所得です。
650万円に税率20%をかけた金額から控除額47万2500円を差し引いた金額が所得税額です。
今回の場合は82万7000円が納税額にあたります。
なお、給与所得がある場合、源泉徴収で給与分の税金は引かれていますので、82万7000円から源泉徴収で支払った分も差し引いた金額を納税します。
不動産投資では住宅ローン控除を受けられないので注意!
住宅ローン控除の条件は「自家用」です。
不動産投資は第3者に賃貸するためですので、自家用にならないため受けることはできません。
そもそも不動産投資には基本的に住宅ローンが利用不可となっているため、住宅ローン控除受けることができないのです。
節税対策としての不動産投資の優位性
不動産投資は節税に効果的といわれています。
購入のための融資の金額や維持費は経費にあたります。
土地は減価償却が認められませんが、建物は減価償却できるため費用に計上できます。
また、生命保険控除を受けるより、団体信用生命保険がついている不動産融資を受けて投資するほうが、節税効果が大きく資産も形成できるという考え方もあります。
団体生命保険にかかる保険料は費用にあたります。
不動産投資による不動産経営が赤字となっても、損益通算で所得控除が増えるため、節税の効果が発生し、保障を受けながら資産形成をするという方法です。
確実な給与収入があって融資を受けることが可能であれば一考の余地は十分にあります。
但し、物件によっては土地の持ち分割合が多かったりすると、減価償却費の計上が少なくなり、節税どころか納税しなければならない事もありますし、『固定資産税』や購入から1度だけ『不動産取得税』の支払いもあります。
税務署が認めてくれている範囲でしっかりと経費計上していくことがとても大切です。
まとめ
サラリーマンなどの給与所得者が不動産投資した場合の確定申告手続きを見てきました。
年末調整を行っても確定申告が必要であるということがわかっていただけたと思います。
近年も芸能人の申告漏れが発覚して騒動になっています。
少しならバレないなどと思わず、確実に申告を行ってください。無申告は必ずバレてしまうものです。
ぜひ本記事を参考にして、正しい納税方法で不動産等投資ライフをお送りください。